2025/7/17
個人再生は失敗することはあるのか?4条件と解決策を徹底解説!
個人再生
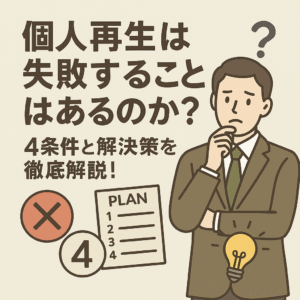
借金で苦しむ方にとって、生活を立て直すための強力な手段の一つが「個人再生」です。
ただし、個人再生の申立てをすれば借金の心配はしなくて良い、とは安易に考えない方が良いでしょう。
その理由は個人再生を認可してもらうにはいくつかの条件があるからです。
今回は、個人再生は失敗することはあるのか・4条件と解決策について、わかりやすくご紹介します。
個人再生とは何か?
個人再生とは、裁判所に申立てを行い、再生計画の認可決定を受け、財産を守りながら借金を大幅に減額し、原則として3年間で完済する制度のことです。
個人再生は債務整理の方法の1つであり、債務整理には個人再生以外に任意整理・自己破産があります。
個人再生に関する7つの特徴
個人再生は民事再生法という法律が根拠になり、裁判所が関与することで、借金を整理し生活を立て直すための法的な救済方法です。
特に、現在住んでいる住宅(マイホーム)を残したい場合におすすめです。
では、個人再生はどのような特徴を持っているのでしょうか。 個人再生の7つの特徴について簡単にご紹介します。
①裁判所に申立てを行い、再生計画の認可決定を受ける必要がある
②税金や養育費以外のさまざまな借金が減額の対象となる
③様々な条件を満たせば現在住んでいる住宅ローン付きの自宅を残せる場合がある
④財産額によっては借金の元本を1/5~1/10にまで大幅に減額できる場合がある
⑤定期的な収入がある人でないと利用できない
⑥返済期間は原則3年であり、特別な事情が認められれば最長5年返済も可能
⑦認可を受けるには個人再生の条件をすべて満たす必要がある
個人再生の2つの種類
個人再生には2つの種類があります。
どちらを使うかは、現在の収入形態や借入先ごとの負債比率によるところが大きいです。
こちらでは個人再生の2つの種類についてそれぞれ解説します。
❶小規模個人再生
小規模個人再生とは、将来に安定収入の見込みがあり、住宅ローン以外の債務総額が5,000万円以下の個人の方を対象にした個人再生のことです。
対象の職業は給与所得者や自営業者です。
債権者の半数以上、または債権総額の過半数の債権者が再生計画に反対(不同意)した場合、個人再生は認可されません。
個人再生を行う方の9割以上が小規模個人再生を利用されています。
❷給与所得者等再生
給与所得者等再生とは、小規模個人再生の要件に加え、給与またはこれに類する定期的な収入があり、その変動幅が小さい個人を対象にした個人再生のことです。
対象の職業は給与所得者です。
債権者の同意は不要で、条件を満たせば裁判所は認可します。
給与所得者等再生は、多くの場合で小規模個人再生より返済額が多くなります。
そのため、給与所得等再生を行われる方は個人再生を行う方の1割未満と少ないです。
個人再生の4条件とは?
個人再生の恩恵を受けるためには、クリアすべきいくつかの条件があります。
もし、これらの条件を知らずに手続きを始めてしまうと時間と労力が無駄に終わるかもしれません。
こちらでは個人再生の4条件について解説します。
継続的な収入の見込みがあること
個人再生は、将来にわたって一定の収入を得る見込みがある個人の方が利用可能な制度です。
なぜなら、認可決定後に返済計画通りに返済を完了する必要があるからです。
債務総額が一定額以下であること
個人再生は、住宅ローンを除く無担保債務(消費者金融、銀行、クレジットカード会社、後払い決済等の負債)の総額が5,000万円以下でなければ利用できません。
個人再生はいくら借金があっても利用できるわけではないです。
無担保債務とは、担保が付されていないすべての債務のことです。
再生計画案が債権者から否決されないこと
提出した再生計画案が、債権者の半数以上、または債権総額の過半数の債権者が再生計画に反対(不同意)した場合、個人再生は認可されません。
こちらは、小規模個人再生の手続きのみが対象です。
過去7年以内に免責許可決定や給与所得等再生の認可決定を受けていないこと
過去7年以内に、自己破産における免責許可決定や給与所得者等再生の認可決定を受けたことがある人は給与所得者等再生の手続きによる個人再生は利用できません。
こちらは給与所得者等再生の手続きの場合です。
以上の4条件を満たすことで個人再生が可能となります。
個人再生は失敗することがあるのか?
個人再生は失敗する可能性が十分あります。
裁判所が公表した令和5年の司法統計によると個人再生の状況は次の通りです。
〇令和5年司法統計 第 109 表(87) (再生既済事件数―事件の種類及び終局区分別―全地方裁判所) ![]() 成功率92%、失敗率8%なので、おおよそ個人再生は10人に1人が失敗しています。
成功率92%、失敗率8%なので、おおよそ個人再生は10人に1人が失敗しています。
ただし、この数値はあくまで個人再生申立ができた方における成功率や失敗率の割合です。実際には、個人再生を弁護士に依頼した後に費用の支払いができなかったり必要書類が提出できなかったりしたことによって個人再生申立がそもそもできずに失敗した場合もありますので、実際には1割以上の方で個人再生に失敗していると言えます。
再生手続終結とは、再生計画案が裁判所に認可され、手続きが正式に認められたことを指します。
この時点で返済計画が確定し、計画通りに返済を始める準備が整います。
ただしこれがゴールではありません。
再生手続終結は個人再生が認められただけであり、実際の返済はここからが始まりです。
個人再生が失敗した場合に起こること
個人再生の手続きは常に順調に進むわけではありません。
予期せぬ事態や条件の不備によって、個人再生が失敗に終わってしまうケースも存在します。
もし個人再生が失敗してしまったら、一体どのような状況に陥るのでしょうか。
こちらでは個人再生に失敗した場合に起こることについて解説します。
借金がそのまま残る
個人再生が失敗すると、個人再生で予定されていた借金の減額がなくなり、元の借金全額(利息含む)を返済する義務が復活します。
債権者の取り立てが再開する
個人再生が失敗すると、債権者の取り立てが再開します。
場合によっては給料や財産が差し押さえられる可能性があります。
マイホームを失うリスク
個人再生が失敗することで、住宅ローン以外の借金も返済しなければならなくなりますので、その返済もあり住宅ローンの返済を滞納してしまうと、マイホームが競売にかけられ失う可能性があります。
手続き費用がすべて無駄になる
個人再生が失敗すると、弁護士費用や裁判所への手数料がすべて無駄になり、お金だけが出て行ったことになります。
自己破産の可能性
個人再生が失敗すると、元の借金全額の返済が復活しますので、現在の収入では生活ができなくなり、自己破産を検討する状態になるかもしれません。
個人再生が失敗する4つのパターン
個人再生が失敗するケースも存在します。
失敗する主なケースは棄却・廃止・不認可・取消しの4つのパターンです。
こちらでは個人再生が失敗する4つのパターンについて解説します。
個人再生の申立てが棄却される
個人再生の申立てが棄却されるとは、個人再生を行うための条件が満たされていないということです。
状況としては、個人再生の手続きが開始される前段階で止められている状態です。
個人再生が棄却される主な場合は以下の通りです。
-
安定した収入がないことが明らかな場合
-
明らかに返済不能な場合
-
債権者の過半数が不同意になると明らかに予想される場合
-
財産を隠して申立を行った場合
-
裁判所に対して虚偽の収支報告を行った場合
個人再生の手続きが廃止される
個人再生の手続きが廃止されるとは、裁判所で進めていた個人再生のプロセスが途中でストップし、打ち切られたということです。
状況としては手続きが始まった後(特に再生計画の作成中や承認前後)に、問題が起きて裁判所が「もうこれ以上続けられない」と判断し、手続きを終了させる状態です。
個人再生が廃止される主な場合は以下の通りです。
-
再生計画案を期限までに裁判所に提出できなかった場合
-
小規模個人再生で債権者の半数以上、または債権額の半分以上の債権者が再生計画に反対した場合
再生計画が不認可される
再生計画が不認可されるとは、提出された再生計画を裁判所が認めないことを決定することです。
再生計画が不認可になると、借金の減額や分割払いの恩恵を受けられずに手続きが終了します。
個人再生が不認可される主な場合は以下の通りです。
-
将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがない場合
-
弁済総額が最低弁済額を下回る場合
- 住宅ローン以外の債務総額が5,000万円を超えている場合
再生計画の取消し
再生計画の取消しとは、一度認可された再生計画に問題があり、認可を取消すことです。
こちらは再生計画が進行中(返済中)に問題が発生し、減額前の債務全額が復活し、返済義務が発生することを意味します。
個人再生が取消しされる主な場合は以下の通りです。
-
返済を滞納した場合
-
個人再生において、債務者が虚偽の申告をしたり、財産を隠したりしていた場合
個人再生に失敗した際の解決策
個人再生が失敗するケースも一定数あります。
ただし、個人再生が失敗したとしてもそれですべてが終わるわけではありません。
解決のための手段は十分残されています。
こちらでは個人再生に失敗した際の解決策について解説します。
個人再生の二度目の申立て
個人再生の二度目の申立てとは、一度目の個人再生の手続きが失敗した後に、再度、個人再生の申立てをすることです。
個人再生は、二度目の申立てをすることは可能です。
ただし給与所得者等再生を再度利用する場合、前回の給与所得者等再生の認可決定が確定した日から7年が経過していなければ、再度の給与所得者等再生の申立てはできません。
ハードシップ免責を申し立てる
ハードシップ免責とは、やむを得ない事情によって再生計画どおりに返済できなくなった場合に残りの借金を免除(帳消し)してもらえる制度のことです。
ハードシップ(hardship)とは、「困難」という意味です。
利用するには裁判所へ申し立てる必要があります。
ハードシップ免責の条件は次の通りです。
・債務者に責任のない理由(失業、病気、事故など)で返済が困難であること
・弁済総額の4分の3以上をすでに返済していること
・ハードシップ免責の決定によって、債権者全体の利益が損なわれないこと
・再生計画を変更したとしても返済を続けていくことが非常に難しいこと
自己破産の手続きを検討する
自己破産とは、借金を返せなくなった人が裁判所を通じて借金を免除にしてもらう法的な手続きのことです。
個人再生が失敗し、借金の返済がどうしても難しい場合、生活を再建するための最終手段として選ばれることがあります。
ただし、自己破産をすると借金は免除されますが、20万円以上の価値がある財産はすべて手放す可能性があります。
個人再生で失敗をしないための3つのポイント
個人再生を確実に成功させ、二度と借金問題に悩まされないためにはどうすればよいのでしょうか。
個人再生を成功に導くためには秘訣があります。
こちらでは個人再生に失敗しないための3つのポイントについて解説します。
個人再生の適正の確認
個人再生の適正確認とは、そもそも自分の負債の対処法に個人再生が向いているのかどうかを確認することです。
負債の整理には、個人再生以外にも任意整理や自己破産があります。
一部分だけをみて決めるのではなく、総合的にみて判断しましょう。
手続きで決まったルールは必ず守る
個人再生の手続きでは借金の減額を受ける代わりに、返済計画や財産の申告、裁判所の指示などに従う義務があります。
ルールを守らないと借金の減額が取消される可能性があります。
個人再生に詳しい専門家に相談する
個人再生の手続きや借金問題の解決に豊富な知識と経験を持つ弁護士や司法書士に、自分の借金状況を話してアドバイスをもらい、手続きを進めるサポートを受けることです。
個人再生は、裁判所を通じた複雑な手続きですので専門家の助けが必須です。
専門家に依頼することで、自分の状況に合った対応やスムーズに手続きを進めてもらえる可能性が高くなります。
また、多くの弁護士や司法書士事務所では、借金問題に関する無料相談を提供しており、個人再生が適しているかどうかを確認できます。
個人再生に関する最新の法改正
現在、個人再生に関する最新の法改正はありません。
個人再生手続がスタートしたのは2001年4月からです。
それ以前は法人向けの手続きのみでした。
2001年4月に民事再生法が施行され、個人もこの手続きを利用できるようになりました。
個人再生は、住宅ローンを除く債務の一部を減額し分割返済しながら、住宅資金特別条項を活用することで、住宅を保持しながら手続きを進めることができる制度です。
まとめ
今回は、個人再生は失敗することはあるのか・4条件と解決策について解説しました。
個人再生は借金を減額し、生活を再建できる有効な手段です。
ただし、裁判所への書類提出や返済計画の作成、債権者との交渉など、専門知識が必要な手続きがたくさんあります。
そのため専門家のアドバイスが不可欠です。
弁護士に相談することで次の3つのメリットを得ることができます。
・債務整理の最適な選択肢の提案
・再生計画案の作成と成功率の向上
・督促や取り立てがなくなり精神的なストレスからの解放
もし現在、借金問題でお悩みであれば、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
セントラルサポート法律事務所
弁護士 安井孟(埼玉弁護士会所属)
債務整理業務に特化した法律事務所を運営しております。

借金・債務整理のご相談はセントラルサポート法律事務所へ
【相談料無料】【着手金不要】
【親身な対応】
